記事の目次
はじめに
M&A案件がどのような手順で進むのか、そのプロセスを知りたい方へ。
この記事では、以下のような内容を解説しています。
この記事の内容
- M&Aの大まかな3ステップ
- 交渉先を選定する手順やプロセス
- 契約内容を交渉する手順やプロセス
- 契約を実行する手順やプロセス
最後まで読んでいただくと、M&Aの一連の流れが分かるようになっているので、ぜひお読みください。
written by @raq_reezy
M&A案件の手順やプロセスは大きく3ステップ
M&Aの流れは、大きく3つのステップで構成されています。
M&Aのざっくりとした流れ
- M&Aの交渉先を選定するステップ
会社や事業を売りたい株主が買ってくれる相手を探す場合と、会社や事業を買いたい側から適切な会社を探してアプローチする場合があります。日本の場合は、売主が買ってくれる相手を探すことの方が多いです。買主側は、ざっくりとした買収金額(バリュエーション)を出して、独占交渉権などが含まれた基本合意書を結びます。 - M&Aの契約内容を交渉するステップ
買収側は、対象会社や事業に隠れたリスクがないか、法務・財務・ビジネス・税務などの面から調査(デューデリジェンス)を行います。問題がなければ、最終的な契約の内容を売主と買主の間で交渉・調整します。 - M&Aの契約を実行するステップ
上のステップで結んだ最終契約書に基づいて、M&Aを実行していきます。クロージングを行ったあと、買主側では買収した企業を自社グループの中にうまく統合していくPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)を行います。
ステップ1:M&Aの交渉先を選定する手順やプロセス
M&Aの最初のステップは、会社や事業の買い手を探して、交渉を開始することです。そのためには、以下のようなプロセスを通るのが一般的です。
M&Aの交渉先を選定する手順やプロセス
- 売主側がティーザーを作成して、ロングリストに送付
- 興味を持った複数の買主候補との間で秘密保持契約(NDA)を結ぶ
- 売主側から、さらに詳しいインフォメーション・メモランダムという事業情報を買主候補に提供する
- 買主候補はどのくらいの値段で買うかバリュエーションを行う
- 売主側は買主候補の中から交渉相手を選んで、交渉を開始する
1. ティーザーの作成と送付
まずは、売主側がティーザー(ノンネームシート)と呼ばれる簡易資料を作成します。ティーザーには、企業名は記載しませんが、事業分野や規模、業績などを書きます。
続いて、買主候補となる会社を20社〜30社ほど探して、ロングリストを作成します。ロングリストには、会社や代表の名前、資本金や業績などを書き出しておきます。
ロングリストでリストアップした買主候補に対してティーザーを送付して、興味を持ってくれた企業があれば、秘密保持契約の締結に進みます。この時点で、可能性のない買主候補は削って、ショートリストにします。
2. 秘密保持契約(NDA)
買主候補がさらに詳しい情報を知りたい場合、NDA(Non Disclosure Agreement)と呼ばれる秘密保持契約を結びます。
売主からすると、自分たちの情報が外に漏れてしまっては、取引先や従業員が動揺する可能性もありますし、類似ビジネスが登場して自分たちのビジネスの価値が毀損することもあります。この時点では、必ず会社や事業が売れると分かっているわけではないので、秘密の保持が担保されることで、初めて売主はさらに詳しい情報を提供できるようになります。
3. インフォメーション・メモランダムの提供
NDAを結んだ後に、売主は会社や事業のさらに詳しい情報が書かれた資料を提供します。これはインフォメーション・メモランダムと呼ばれます。
複数の買主候補がいる入札形式などの場合は、インフォメーション・メモランダムの提供と同時に、どのように売却を進めていく予定なのか、基本条件や買主の選定方法などが記載されたプロセスレターが交付されます。
4. バリュエーション
各企業は、その企業や事業の価値算定(バリュエーション)を行います。
バリュエーションの基本は、その事業が将来的に生み出すキャッシュフローを割り戻すDCF法です。しかし、単純に与えられた情報をもとにDCF法をしたのでは、全ての買主候補でだいたい同じ価格になってしまいます。
そこで、各買主候補は自社とのシナジーを生み出すことで、さらに利益やキャッシュフローが拡大することも視野に入れて、バリュエーションを行うことで、他社よりも高い入札をすることが可能になります。
5. 基本合意書(LOI)の締結
各買主候補からのバリュエーションや条件が出揃ったら、売主はどの会社と交渉するかを選定します。
選定後は、デューデリジェンスに入っていきますが、その前に基本合意書(LOI)を締結するのが一般的です。基本合意書には、M&Aのバリュエーションや条件などを記載します。LOIは、あくまでもその時点での仮の合意であり、最終的な契約書ではありません。そのため、内容の一部(秘密保持や独占交渉権など)を除いて、法的拘束力を持たせないのが一般的です
ステップ2:M&Aの契約内容を交渉する手順やプロセス
基本合意書(LOI)を結んだあとは、買主が売主の状況をさらに精査に調べて、基本合意書の条件でM&Aを進めて問題がないかを確認します。これをデューデリジェンスと呼びます。
問題がなければ、LOIの内容を基本として最終契約を交渉します。大きな問題が発覚すればM&Aが白紙になることもありますし、LOIの内容からの条件変更が交渉されることもあります。
M&Aの契約内容を交渉する手順やプロセス
- 買主側が各種DD(デューデリジェンス)を実施
- 双方で最終契約の内容を交渉
1. 各種DD(デューデリジェンス)の実施
買主は、まだインフォメーション・メモランダム程度の内容でしか会社や事業のことを把握できていません。そこで、各種デューデリジェンスを行い、未把握のリスクや問題がないかを精査していきます。
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスとは、その事業や会社の会計(損益計算書やバランスシートなど)を中心に、リスクや問題がないかを調べていくデューデリジェンスです。インフォメーション・メモランダムなどで提示されたような売上や利益が本当にあるのか、粉飾会計などが行われていないかを確認するとともに、バリュエーションを計算するときに立てた将来計画の実現可能性なども確認します。
法務デューデリジェンス
法務デューデリジェンスとは、売主が他者との間に問題やリスクのある契約を結んでいないか、買主が当初想定していた通りの権利・義務関係であるかを確認するものです。例えば、極端な例ですが、売主が保有していると思っていた知的財産権が実は存在しなければ、それは事業価値に直結します。そうしたリスクや問題がないかを調べて、存在した場合には対策を考えます。
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスは、売主の税務リスクを確認します。また、それに加えて、どのようなストラクチャーでM&Aを行うのが最も税金面で効率がよいかというタックスプランニングの前提となる状況確認も行います。
事業デューデリジェンス
事業デューデリジェンスとは、その事業自体の収益性や継続性を確認するものです。バリュエーションのときに立てた事業計画の妥当性などもあわせて確認します。
2. 最終契約の内容を交渉
各種DDが終わると、買主側は売主側に対して、最終的な条件や買収価格を提示します。売主にとって、それが納得のいく提示であった場合には、双方で最終契約の内容に関する協議に入ります。
最終契約書では、以下のような内容が記載されます。
最終契約書に記載される内容
- M&A価格
- 表明保証
- M&Aが実行される条件(クロージング条件)
- M&A後の補償事項
- 誓約事項
- クロージング手順
ステップ3:M&Aの契約を実行する手順やプロセス
M&Aの最終契約ができたら、その契約内容を実行するプロセスに入ります。これをクロージングといいます。
また、クロージングで会社や事業が買主側に渡ったあと、買主側では、事前に立てた将来計画に沿って事業を運営できる状態をつくっていく必要があります。これをPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)といいます。
M&Aの契約を実行する手順やプロセス
- クロージングの準備
- クロージングの実行
- ポストクロージングの実行
- PMI(経営統合)の実行
1. クロージングの準備
M&Aにおいては、最終契約を結んだら、すぐに実行できる訳ではありません。大体の場合は、クロージングの条件が付されることが多いからです。
例えば、現在の監査役や経営陣が辞任すること等が条件に入っていることもあります。こうしたクロージングの条件を売主側は揃える必要があります。その他にも、デューデリジェンスにおいて見つかった事業や会社の瑕疵を治癒することが条件の場合もあります。
クロージングの準備が整ったら、実行のフェーズに移ります。
2. クロージングの実行
クロージングを行うと、事業は買主のものになります。クロージング当日は、ざっくりと以下のような流れで行われるのが一般的です。
クロージング実行のイメージ
- すべての手続き書類や必要な条件が整っていることを買主が確認
- 買主が買収対価を提供
- 売主が着金を確認
- 必要書類を売主が買主に提供
3. ポストクロージングの実行
場合によっては、ポストクロージングの手続きが発生することもあります。
例えば、株主総会を開催して新任役員を選定するなどがあります。また、売主が対象会社の債務に対して行っている個人保証があれば、それを解除するなども行われます。
4. PMI(経営統合)の実行
M&A自体の直接的な手続きは、ポストクロージングまでで終了していますが、買主側においては、PMIを適切に実行できるかが重要です。
今後の将来計画に沿った人員体勢の整備や、自社の既存事業とのシナジーを生み出すなど、バリュエーション時の前提をきっちりと実行できなければ、支払った対価に見合う成果が得られなくなってしまうからです。
PMIが行われて、対象会社や対象事業が安定して運営される体制が整えば、広い意味でもM&Aが終わりとなります。
まとめ
今回は、M&Aのざっくりとした手順や流れを解説しました。
- 交渉相手を探すステップ
売主側でティーザーやインフォメーション・メモランダムを作成して、秘密保持契約(NDA)を結んだ買主候補に送付。買主候補はバリュエーションを行い、売主側は交渉相手を選定して基本合意書(LOI)を結ぶ - 最終契約内容の交渉を行うステップ
買主側は、財務DD、法務DD、税務DD、事業DDを行う。両者で最終契約の内容を交渉して締結する - 最終契約内容を実行するステップ
締結された最終契約の内容を実行して、M&Aの手続きを完了させる。M&A後、買主側ではPMI(経営統合)を行う
以上です。




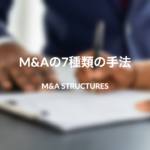



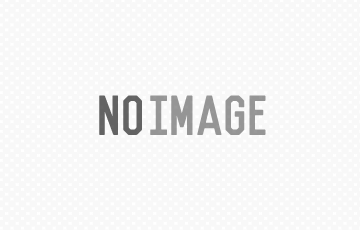

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)






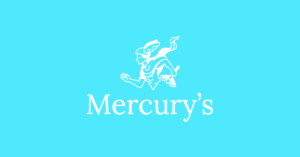




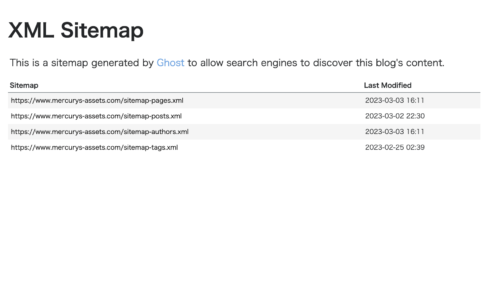


コメントを残す