オディロン・ルドン(画家)
オディロン・ルドンとは オディロン・ルドン(1840年 – 1916年)は、フランスの象徴主義の画家として知られています。彼はボルドーで生まれ、病弱な幼少期を過ごした後、15歳で画家のスタニスラス・ゴランから…
 芸術家
芸術家
オディロン・ルドンとは オディロン・ルドン(1840年 – 1916年)は、フランスの象徴主義の画家として知られています。彼はボルドーで生まれ、病弱な幼少期を過ごした後、15歳で画家のスタニスラス・ゴランから…
 美術・芸術
美術・芸術
写真家 ジュリア・マーガレット・キャメロン オディロン・ルドン
 芸術家
芸術家
ジュリア・マーガレット・キャメロンとは ジュリア・マーガレット・キャメロン(1815年 – 1879年)は、19世紀ヴィクトリア時代のイギリスを代表する写真家として広く知られています。彼女が写真を始めたのは、…
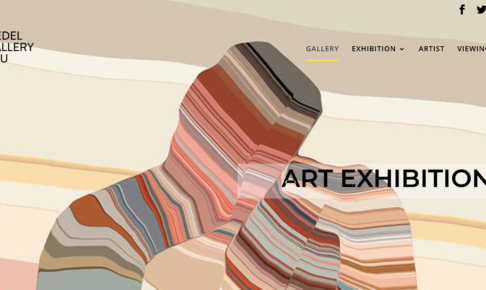 アート・デザイン
アート・デザイン
Medel Gallery Shuとは Modern Art Gallery Tokyo「Medel Gallery Shu」は、帝国ホテルプラザの2階にある商業ギャラリーです。 株式会社コンプリートコネクション(代表取…
 日本庭園にあるもの
日本庭園にあるもの
はじめに 日本庭園の植物について詳しく知りたい方へ。 この記事では、日本庭園の役木(庭木)や下草について、その種類などを詳しく解説しています。 日本庭園の植物について、その種類などを理解できるようになっていますので、ぜひ…
 日本庭園にあるもの
日本庭園にあるもの
はじめに 日本庭園の石組にはどんなものがあるか興味がある方へ。 この記事では、以下のような内容を説明しています。 この記事を読んでいただければ、日本庭園の主要な石組について理解して鑑賞を楽しめるようになります。せひ最後ま…
 日本庭園
日本庭園
はじめに 日本庭園の特徴や、日本庭園にあるものを知りたい方へ。 この記事では、以下の内容を説明しています。 まずは、この記事をざっくりと読んでいただいた上で、さらに細かく説明している個別の記事を読んでみてください。 wr…
 日本庭園の種類
日本庭園の種類
はじめに 露地(茶庭)について、詳しく知りたい方へ。 この記事では、以下の内容を説明しています。 露地(茶庭)について、ひと通り分かるようになっているため、ぜひ最後までお読みください。 written by @raq_r…
 日本庭園の種類
日本庭園の種類
はじめに 枯山水庭園について詳しく知りたい方へ。 この記事では、以下の内容を解説しています。 最後まで読んでいただくと、枯山水庭園について深く理解することができます。ぜひお読みください。 written by @raq_…
 日本庭園の種類
日本庭園の種類
はじめに 池泉庭園について詳しく知りたい方へ。 本記事では、以下のような内容を解説しています。 この記事を読んでいただければ、池泉庭園の基礎知識を網羅できますので、ぜひ最後までお読みください。 written by @r…
 日本庭園
日本庭園
はじめに 日本庭園の種類・様式を知りたい方へ。 この記事では、以下の内容を説明しています。 この記事を読んでいただければ、日本庭園の基本となる3つの形式がわかります。また、それぞれの詳しい解説にもリンクしていますので、ぜ…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
陰陽石組とは 陰陽石組とは、男性器に見立てた陽石と女性器に見立て陰石を組み合わせた石組です。 これは子を授かりたいという願いから庭に置かれるようになったもので、特に江戸時代には後継者の不在は改易の対象であったため、大名た…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
侘び・寂び(わび・さび)とは 侘び・寂び(わび・さび)とは、室町時代に禅宗などの影響を受けて主流になった、美しさについての価値観です。 侘び・寂びの価値観では、経年変化などによって、汚れたり、欠けたり、寂れたりと劣化した…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
露地(茶庭)とは 露地とは、邸宅と茶室の間に設けられた日本庭園を指します。 語源は「路地」であり、室町時代初期には、邸宅から茶室までの道のりのことでした。やがて、お茶の文化を大成させた千利休の時代になると、禅宗の影響を受…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
落葉樹とは 落葉樹とは、もみじなど、秋になると紅葉して、冬に葉が落ちる木を指します。逆に、冬でも葉が茂っている松などの木は常盤木(常緑樹)です。 役木や景色づくりにおいては、落葉樹と常緑樹をバランスよく配植します。例えば…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
寄付(袴付)とは 寄付(袴付)とは、露地(茶庭)の邸宅に用意された着替えスペースです。 寄付で衣装を着替えると、庭に出て、外露地の外腰掛で他の客が揃うのを待ちます。その後、中門あたりにある亭主石のところで亭主と挨拶を済ま…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
寄植えとは 寄植えとは、いくつかの木を寄せて植えることを指します。 大きな木を寄せて植えるときには、気勢がぶつからないようにすることが大切です。 また、低木を寄植えしたものは植え込みといいます。植え込みに刈り込みを行って…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
雪吊りとは 雪吊りとは、雪の重みで松の枝が曲がって折れないよう、それぞれの枝を縄で吊る作業を指します。 一般的なのは、幹付近に柱を立てて、そこから枝の先まで縄を張る方法で「りんご吊り」と呼ばれます。 雪吊りは兼六園で行わ…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
遣水とは 遣水とは、池泉庭園に設けられた川のような部分で、池へと水を引いてくることを目的としています。 平安時代の池泉庭園である寝殿造系庭園、その発展系の浄土式庭園などにおいては、風水の考え方から、庭の東に青龍に見立てた…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
役木とは 役木とは、庭に配植される樹木の中で、特定の役割を担っているものを指します。 江戸時代に書かれた『築山庭造伝』の後編には、古くから日本庭園にみられる役木が解説されています。 例えば、庭のメインとなるシンボルツリー…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
幹巻きとは 幹巻きとは、冬の間、松の幹などにワラなどを巻きつけることを指します。 樹木には、表皮の裏に形成層という部分があり、根から吸い上げられた水はここを通って枝葉に向かいます。しかし、冬になるとこの活動が休眠して、形…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
ビリ砂利とは ビリ砂利とは、川の砂利のような形状の砂利を指します。 昔は、川の砂利をふるいにかけたものが用いられていましたが、現在では河川の砂利の採取は河川法によって禁じられているため、人工的に川の砂利に似たような形状の…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
舟石とは 舟石とは、池泉庭園において、池の中に船に見立てて置かれる石を指します。 特に、神仙蓬莱石組においては、蓬莱島に不老長寿の薬を取りに行く船を表現するために舟石が用いられます。蓬莱島に向かう船を表すときは身軽で少し…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
配植とは 配植とは、日本庭園において、どのように木や草を植えるかを表します。 配植で気をつけるべきポイントはたくさんあります。 例えば、落葉樹と常盤木(常緑樹)のバランスがあります。落葉樹は紅葉などが綺麗ですが、落葉樹だ…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
二重露地とは 二重露地とは、露地(茶庭)の中で、中門を境に内露地と外露地が分かれているタイプのものを指します。 お茶に招かれた来客は外露地にある外腰掛で参加者が揃うのを待ちます。参加者が揃うと、客を招いた亭主は、中門のあ…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
常盤木(常緑樹)とは 常盤木とは、松などの常緑樹を指します。年中、葉が繁っている常盤木は、生命力や長寿の象徴でもあります。 常盤木と落葉樹はバランスよく配植する必要があります。例えば、秋には紅葉する落葉樹が美しいですが、…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
亭主石とは 亭主石とは、露地(茶庭)の中門(中潜)の内側に置かれる石です。 来客が外腰掛に揃うと、亭主が亭主石のところまで出迎えるため、亭主石という名前で呼ばれています。 亭主石のところで挨拶を済ませると、みんなで内露地…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
飛石とは 飛石とは、庭を歩くときに、土や苔で履き物が汚れるのを防ぐために地面に並べられた石です。千利休によって、露地(茶庭)に導入されたといわれています。 飛石は、いわば道の役割を果たしますが、直線的に来客を茶室まで導く…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
鶴亀石組とは 鶴亀石組とは、鶴に見立てた鶴石組と、亀に見立てた亀石組を組み合わせた石組です。 「鶴は千年、亀は万年」といわれるように、鶴亀は長寿の象徴として知られており、縁起の良い「鶴亀蓬莱の庭」として、神仙蓬莱石組とあ…
 日本庭園の用語集
日本庭園の用語集
手水鉢(ちょうずばち)とは 手水鉢とは、主に露地(茶庭)に置かれる、手を清めるための水を流す器を指します。 元々は、神社やお寺で境内に入る前に置かれていた手水鉢が、お茶の文化が大成した桃山時代に、露地(茶庭)にも取り入れ…