記事の目次
はじめに
実存主義哲学の代表格であるマルティン・ハイデガーの思想や人生について詳しく知りたい方へ。
この記事では、以下のような内容を解説しています。
この記事の内容
- マルティン・ハイデガーとは
- マルティン・ハイデガーの『存在と時間』の解説
- ハイデガーに影響を与えた哲学者
- ハイデガーの私生活
最後まで読んでいただくと、ハイデガーについてかなり理解できるようになっていますので、ぜひお読みください。
また、本記事は、以下の解説書を参考にしています。ハイデガーのいう「存在」と従来の西洋哲学における「存在」は結局何が違うのかということを何年も考え続けた轟孝夫という専門家による入門書です。興味を持たれた方は、ぜひ読んでみてください。
written by @raq_reezy
マルティン・ハイデガーと実存主義の思想とは

マルティン・ハイデガーと実存主義の思想とは(Mediumより)
マルティン・ハイデガー(1889年9月26日 – 1976年5月26日)は、西洋哲学の現代思想のひとつである「実存主義」と呼ばれる考え方に括られる哲学者です。若い頃は神学の研究者でしたが、途中から哲学へと転向しています。
自然科学が発達して、従来のキリスト教の価値観が崩壊したヨーロッパにおいては、人々は人生の意味や目的を喪失していました。自然科学がキリスト教と決定的に異なるのは「世界の仕組みや成り立ちを理解するのには役に立っても、その世界の中で自分が生きる意味を与えてくれることはない」という点です。
そのため、宗教が崩壊した世界において「人の生きる意味」を補ってくれる考え方が必要となり、それに答えたのが「実存主義」と呼ばれる哲学でした。
ハイデガーは、ひとことで言うと、人間が「文脈や感情を伴って世界の様々な存在を認識するところ」に、人間の意味を見出しました。
例えば、目の前に「水」があるとします。これは自然科学的に説明すると、H2Oだということになりますし、人間がいようがいまいがH2Oは存在しています。しかし、人間はこれを飲み水として認識したり、川として認識したりします。また、飲み水であっても、喉が乾いているときと潤っているときでは、それを異なる存在として認識するでしょうし、コップの中に入ったものと机の上にこぼれてしまったものでは、また異なる存在として認識するでしょう。ここに人間の存在する意味を見出したのです。
ハイデガーは、先ほどの例でいうところの「水(H2O)」を「存在者」、「人間」を「現存在」、存在者(H2O)がそれぞれの現存在にとって固有の文脈や意味を持って現れる様子を「存在」と呼びました。また、「現存在」である人間は、世間の価値基準等に流されずに、自分の主体性を取り戻すことによって、それぞれにとってユニークな「存在」として「存在者」を認識できるようになると考えました。
ハイデガーの『存在と時間』をわかりやすく解説

マルティン・ハイデガーの『存在と時間』をわかりやすく解説
『存在と時間』は未完成
『存在と時間』は、ハイデガーが執筆した著作で、20世紀を代表する哲学書だと評価されています。しかし、『存在と時間』は実は未完成の著作であることを知らない人もたくさんいらっしゃると思います。
ハイデガーは、もともと『存在と時間』には前編と後編があるとして、前編では「存在」の基本的な仕組みや「現存在」の分析をした上で、後編ではいよいよ「存在」の具体的な分析に入っていく想定でした。
しかし、『存在と時間』の後編は結局、完結することはありませんでした。そもそも、ハイデガーは原稿を未発表のまま書き溜めておき、大学内での出世等の理由で成果が必要な場合に出版していました。また、ハイデガーは一時期ナチス運動に傾倒していたことで、第二次世界大戦中は政治的な駆け引きも多く、その後には教職を一時続けられないなど生活が不安定な時期もありました。いずれにせよ、僕たちは『存在と時間』の全容を知ることはできません。
しかし、少なくとも前編の内容は分かるわけなので、その内容を紹介していきたいと思います。
西洋哲学は「存在」を忘れていた(存在忘却)
ハイデガーは、西洋哲学においては、ずっと「存在」というものが取り扱われてこなかった(= 忘れられていた)と訴えました。これを「存在忘却」といいます。
しかし、ギリシャにおいて、タレスが「万物の根元は水である」と言ってから、キリスト教が広まって「世界は神様が作った」と説明されていた時代を経て、自然科学によって世の中のあらゆるものが存在する理由が解き明かされるまで、常に哲学は「世の中はどうして存在するのか」を考えてきました。
では、ハイデガーはどうして、存在が忘却されていると考えたのでしょうか。それは、個々の人間がどのように存在を受容するかという「人間の主観」を伴う「存在」を考えてこなかったからです。
ハイデガーは、様々なものが単に客観的に存在しているだけでなく、人間がそれらを各自の主観や意味・文脈を伴って受容・認識して、初めて「存在」であると考え、そうした意味での「存在」を西洋哲学は考えてこなかったと批判したのです。
「存在者」と「存在」の違い
ハイデガーが、単に客観的に存在するもの(= 存在者)と、人間がそれを各自の主観や文脈を伴って受容したもの(= 存在)を分けて考えるようになった背景には、彼の師であるフッサールの影響があります。
ハイデガーはフッサールの生み出した「現象学」の考え方を武器として自由自在に使いこなして、若い頃に研究していた神学などを再解釈することで、独自の哲学を打ち立てた哲学者であるといえます。
そこで、まずはフッサールが生み出した「現象学」について、理解を深めてみましょう。
(1)フッサールの現象学
フッサールの現象学については、以下の「哲学チャンネル」の動画が非常にわかりやすいので、こちらを見ていただくことをおすすめします。
一応説明しておくと、世の中では一般的に、以下のように世界を認識していると考えています。
一般的な認識プロセスの理解
- まず物事が存在する(客観)
- 人間がそれを認識する(主観)
例:「りんご」が存在して、人間がそのりんご(と呼ばれる赤い果物)を認識する
しかし、人間が物事を認識して思考するプロセスを、フッサールは以下のように捉え直すことで、根本的に哲学を見直すことができると考えました。
現象学における認識プロセスの理解
- まず人間が様々な体験をする(主観)
- それらの体験から物事を認識する(客観)
例:人間が「目の前に赤い果物がある」という体験して、知識や過去の経験などから「りんご」と認識する
そして、この主観的な体験から客観的な物事を認識するプロセス(= ノエシス)を研究対象にしようと考えたのです。
フッサールがこのような「現象学」を生み出した背景としては、科学技術が飛躍的に進歩して、一歩間違えれば戦争など人間に大惨事をもたらすようになっていく中で、「絶対に間違えのない世界の捉え方」が求められたということがあります。
では、絶対に間違えのない世界の捉え方とは何でしょう。
そもそも近代という時代は、デカルトという哲学者が「我思う故に我あり」といったところから始まりました。彼は、世界の全てを疑ってみたときに、世界の全てを疑っている自分、つまり「自分の意識(理性)」だけは疑いようのない真実だと考えました。また、次に確からしいものは、自分の意識で感じる五感でした。
フッサールは、このように「自分の意識(理性)」と「五感」が最も確からしいのであれば、それらを大前提とした世界の捉え方こそが、間違えようのないものではないかと考えたのです。だから、一般的な世界の捉え方である「客観→主観」ではなく、「主観(意識や五感)→客観」という人間の認識プロセスこそを研究すべきだと訴えました。
(2)視点の逆転
さて、フッサールの説明が長くなりましたが、ハイデガーはフッサールの弟子ですから、フッサールの現象学の影響を大きく受けています。
ただし、ハイデガーがフッサールと違う点としては、フッサールが「人間がどのように物事を認識するか」という「人間の認識プロセス」の方に興味を持ったのに対して、ハイデガーは「人間によって認識される物事(= 存在)」の方に興味を持ちました。これらはコインの表裏のようなものでもあります。
また、ハイデガーは「存在とは何か」を考えていくなかで、「存在とは何かを正しく理解するためには、そもそも存在を認識する人間(現存在)の側がどのような状態であれば正しく存在を認識できていると言えるのかを考えるべきだ」というところにまで考え方を発展させていきます。この部分も「意識(理性)は間違えようのないもの」というデカルトの考え方を大前提に置いたフッサールとは少し考え方が違っています。
こうして、ハイデガーは現象学の枠組みを超えて、実存主義の哲学者の一人となっていったのです。
「存在」を了解する「現存在(世界-内-存在)」とは

「存在」を了解する「現存在(世界-内-存在)」とは
それでは、僕たち「人間(= 現存在)」について、ハイデガーがどのような捉え方をしていたかを、さらに深くみてきましょう。ハイデガーの有名な「ダスマン(世人)」などの概念はここから出てきます。
(1)「現存在」は「存在」を了解する
まず、上でも書いてきたように、ハイデガーは、単に客観的に存在している物事(= 存在者)と、それが各個人(= 現存在)にとって、異なる意味や文脈を伴って現れたもの(= 存在)を別のものとして考えました。
そして、僕たちは何の意味も文脈もなく物事を認識することはありませんから、常に何らかの「存在」として「存在者」を見ていることになります。
このように、意味や文脈を伴って現れる「存在」を「現存在」が認識・受容することを、ハイデガーは「存在を了解する」と呼びます。なお、「了解」というと、まるで人間が選り好みして「存在」を認識・受容できるような響きですが、当然、「現存在」は目に入ってきた「存在」は何でも了解してしまいます。
このように「現存在」は、世界のさまざまな物事が否応なく自分ごととして現れる場所です。そういった意味で、ハイデガーは「現存在」を「世界-内-存在」とも呼びました。
(2)「存在」の了解には「情態」が伴う
また、ハイデガーは「現存在」が「存在」を了解するとき、そこには常に「情態」が伴うと考えました。
たとえば、りんご好きな人であれば「熟れた食べ頃のりんご」という「存在」を了解すると、同時に「おいしそうだなぁ」と感じるでしょう。学生であれば「夏休みが終わる直前になって山々と残っている宿題」という「存在」を了解すると、同時に「面倒くさいなぁ」と感じるかもしれません。
このように、「現存在」が何らかの「存在」を了解するときには、常にそこに「情態」が同時に伴っています。
(3)「存在」とは何かを考えるには「現存在」の分析が必要
さて、「存在」とは「存在者」が「現存在」に意味や文脈を伴って了解されたもので、さらに同時に「情態」が発生するというところまで分析を深めることができました。
では、そのような「存在」とは、さらに具体的にはどういうものなのかを考えていきたいのですが、「存在」は常に「現存在」によって了解されなければ存在し得ないものですから、「現存在」の「存在を了解する機能」が正常に作動していなければ、本来の正しい「存在」を分析することができない、とハイデガーはいいます。
そこで、ハイデガーは「存在」について深く入っていく前に「現存在」の分析を行います。
「現存在」の分析:ダスマン(世人)へと頽落している

「現存在」の分析:ダスマン(世人)へと頽落している
(1)「存在」を本来的(主体的)に了解することから逃避している
ハイデガーは、一般的に「現存在」は日々の生活の中で世間に埋もれて、主体性を失った状態になっていると考えました。これを「ダスマン(世人)」といいます。
なぜ「現存在」が「ダスマン」になっているかというと、「現存在」としてあらゆる物事(存在者)を主体的に了解して「存在」させるのは、とても面倒で重荷な作業だからです。自分が「現存在(世界-内-存在)」であり、そこに次々と「存在者」が意味や文脈を伴って現れ、自分がその「存在」を了解しなければいけないということは、各個人がコントロールできることではなく、生まれながらにして背負わされている重荷だとハイデガーは考えたのです。ここには若い頃に研究していた神学(キリスト教)における「原罪」のようなイメージがあります。
ハイデガーは、このように自分の意志とは無関係に「現存在」として存在させられているという事実を人間が認識している(こうした事実の「存在」を了解している)からこそ、人間は「漠然とした不安」という「情態」を常に抱えているのだといいます。
「現存在」は、このような「物事を自分の主観に基づいて了解するという重荷」から逃避して「ダスマン」へと頽落しているのです。超ざっくり言い換えると「自分(の価値観)と向き合うことを避けている」ということです。
(2)世間的な規範によって非本来的に「存在」を了解している
さて、「ダスマン」に頽落している状態の「現存在」は、当然ながら「存在を主体的(本来的)に了解する」という作業から逃避しているわけですから、本来的な「存在」を了解できていません。
代わりに、「ダスマン」は世間的な規範によって、非本来的に「存在」を了解しているとハイデガーは分析しています。言い換えると、世の中の多くの物事について、本来は自分自身の意見や感想が心の奥にはあるけれど、それからは目を背けて、世間がどう評価しているかの方を採用しているということです。
例えば、他人を評価するときに、僕たちは自分自身の感性等でその人と向き合って理解するよりは、他の人がその人についてどのような噂をしているかに基づいて評価することが多いのではないでしょうか。その方が、自分に責任がなく、気が楽な感じがします。これが「ダスマン」という状態です。
「ダスマン」は、自分の本当の主観に基づいて、本来的に物事の存在を了解することから逃避しています。そのため、他者が物事をどう評価しているかを確認するための噂話や情報収集が好きで、またじっくりと何かと向き合わなくてもよいように、常に気晴らしや暇つぶしを求めているという特徴があります。
さて、「ダスマン」の状態が必ずしも悪であるというわけではありませんが、ハイデガーは「存在とは何か」に興味を持っているわけですから、「現存在」が「ダスマン」に頽落して機能していない状態では、「存在」の分析を進めることができません。
そこで、ハイデガーは「現存在」はどうすれば本来性を取り戻せるかを考えることとなります。
「現存在の分析」:「死への存在」と自覚することで本来性を取り戻せる

「現存在の分析」:「死への存在」と自覚することで本来性を取り戻せる
(1)「死」は「現存在」にとっての全てである
まず、「現存在」が本来性を取り戻すためには、「現存在」を全体として捉えて、それに向き合う必要があります。
そして、ハイデガーは「死」に行き着きます。人間が死ぬと、もう世界の中にある「存在」を了解することは出来ないわけなので、「死」とは即ち「現存在」が全体として終わることを意味します。ハイデガーは「現存在」を「世界-内-存在(世界の中に投げ入れられて、そこに様々な存在が現れて、それを了解する存在)」と捉えましたが、「現存在」が投げ入れられた「世界」というのは、「避けようのない死に向かっていく時間の流れ」でもあるのです。
また、「死」はどこまでいっても「世界の終わり」ではなく「自分自身(にとっての世界)の終わり」なので、世の中の他の物事から隔絶されているという点でも、自分自身(現存在)と向き合うのに好都合に思えます。
このような考察から、ハイデガーは死を「他ならぬ自分自身の、他から隔絶された、確実であり、またそのようなものとして未規定の、追い越しへない可能性」であると規定しています。
(2)「死」と本来的に関わることで本来性を取り戻せる
しかし、「現存在」は通常、「死」という「存在」と主体的に向き合うことからも逃避しています。
「自分はさしあたりまだ死なない」と非本来的な向き合い方をしており(「死」という「存在」を非本来的なあり方で了解しており)、「いつか必ず訪れる確実なもので、いつ訪れるかもわからない」という本来の「死」という「存在」と向き合うことからは逃げているのです。
さて、「死」を本来的に了解することで、「現存在」は自分が「他から隔絶された存在」であるということも同時に了解することとなります。なぜなら、「死」という「存在」は、本来、自分が「他から隔絶されている」という事実の「存在」を内包しているからです。
簡単に言い換えると、「本当の意味での死」と向き合って受け入れるということは、「自分が死んでも、世界が終わるわけではなく、自分だけがひっそりと死ぬ」、つまり「自分自身は究極的には世界と隔絶されている」という事実と向き合って受け入れるということでもあるのです。
このようにして、ハイデガーは「死」という「存在」と向き合うことで、「現存在」はその本来性(主体的な世界との関わり方)を取り戻せる、もしくは、少なくともそういう本来的な生き方を可能性として認識できると考えました。
そして、本来性を取り戻した「現存在」が「存在」をどのように了解するかを分析していくことで、「西洋哲学がずっと取り扱ってこなかった”存在”とはズバリどのようなものなのか」という最初の問いに迫ることができるはずだったのですが、結局、『存在と時間』は壮大な前置きだけを残して、未完のままとなってしまったわけです(笑)。
『存在と時間』まとめ
長くなってしまったので、『存在と時間』の解説をまとめておきたいと思います。
- 西洋哲学の存在忘却
西洋哲学はその長い歴史において、客観的な意味での存在(= 存在者)しか取り扱っておらず、各個人(= 現存在)にとっての意味や文脈を伴った存在者のあり方(= 存在)をというものを取り扱ってこなかった。従来の西洋哲学には、このように大きな欠陥があり、真の意味での「存在」とは何かを研究しなければならない。 - 「現存在」の頽落による不都合
「存在」とは何かを研究するには、そもそも「存在」を主観や意味・文脈を伴って了解する「現存在」が正常に機能していなければならないが、「現存在」は大抵の場合、主観ではなく、世間的な価値基準に基づいて「存在」を非本来的に了解する「ダスマン」へと頽落しており、機能不全を起こしている。これでは「存在」を研究することができない。 - 「現存在」は「死」と向き合うことで本来性を取り戻せる
「現存在」にとって「死」というのは特別なものである。それは「現存在」が歩んでいる時間の先に必ずある不可避なものであり、全てであり、また極めて個人的なものである。だから、「死」という「存在」と向き合って、本来的に了解することができたなら、「現存在」は主体性を取り戻すことができる。 - これで「存在」を研究することができる
「現存在」が頽落した「ダスマン」の状態から本来性を取り戻す方法がわかったので、これで本来性を取り戻した「現存在」が「存在」をどのように了解するかを分析することで、「存在」というものを研究することができる。「存在」の研究を楽しみにお待ちください(未完成)。
ということになります。
『存在と時間』の意義
ここまで見てきたように『存在と時間』には、「過去の西洋哲学全体を批判するようなダイナミックさ」と「未完成であるというしりすぼみ感」があります。ハイデガーの哲学は、めちゃめちゃ派手に風呂敷を広げて、それを畳み切らずに終わったものといえるでしょう。
そのため、後に続く哲学者たちに多大な影響を与えます。
自身の講義を受けていた学生のハンナ・アーレントや、フランスで実存主義の哲学をすすめたサルトル、構造主義のミシェル・フーコー、ポスト構造主義といわれるドゥルーズなど、様々な現代思想のスター級の哲学者がハイデガーの影響を受けました。
ハイデガーとナチスへの傾倒
ハイデガーは、ナチス運動が「既存の世界の枠組みに反旗を翻して、ドイツのナショナリズムを取り戻そうとする様子」に「現存在が、世間に流されることなく本来性を取り戻した、主体的な姿」を見出すようになり、ナチスの運動に賛同するようになっていきます。
ナチスに入党して、その支持を受けてフライブルグ大学の総長に就任すると、以下のような発言をしてナチスを擁護しました。
ハイデガーによるナチス擁護発言
- 「ナチ革命は我々ドイツの現存在を完全に変革している」
- 「民族は、こうした問い(我々が何者なのか)を発することによって、その歴史的現存在を耐え、危機と脅威の中でそれを堅持し、その偉大なる使命の中にまでそれを持ち込むことができるのであって、民族がこうした問いを発することこそが、民族が哲学的に考えるということであり、それが民族の哲学なのである。」
- 「総統に臣従するとは、ドイツ民族が、労働の民族として、その自然のままの統一、その素朴な尊厳と、その真の力を見つけ出し、労働国家として恒久性と偉大さを勝ちとることを、断固として不断に望むことなのであります。こうした未曾有の意志を抱いている人物、我々の総統アドルフ・ヒトラーに、ジークハイル三唱!」
Wikipediaより
人間の全体主義的なあり方を「ダスマン」として非本来的だとしたハイデガーが、全体主義の代表例ともいえるナチス運動に傾倒してしまったことは、実に残念であるとともに、真に主体的・自由であることの難しさを示しているようにも思えます。
「主体性を取り戻す」というのは、あくまでも個人レベルで行われるべきことであり、それを「ドイツ国民としての主体性を取り戻すべき」というように特定の集団レベルに安易にあてはめてしまうことは、全体主義の促進と紙一重であるため、特に注意する必要があるといえるでしょう。
ハイデガーに関係する哲学者を紹介
アリストテレス
- 執筆中
アウグスティヌス
アウグスティヌスは神学・スコラ哲学の代表です。キリスト教を哲学的に扱うというアウグスティヌスの作法は、ハイデガーとも親和性があり、ハイデガーはたびたび著作の中でアウグスティヌスの書物を参照するようにと指示しています。
マルティン・ルター
マルティン・ルターもまた、ハイデガーにとって大きな影響を持つ思想家でした。マルティン・ルターは『聖書』に書かれていることだけが正しいものだとして、カトリック教会の権威を批判しましたが、このように書物と論理に基づいて思考を展開する姿勢は哲学と通ずるものがあります。
ハイデガーは、たびたび自身の著作の中で、ルターを参照するようにと指示しています。例えば、ルターはアダムとイブが知恵の実を食べたあとに、神の音を聞いて隠れた様子を「嘆かわしい堕落」と記しましたが、「現存在」が本当の自分から逃避している様子のイメージはここから来ています。
セーレン・キルケゴール
キルケゴールは、自身の人生に絶望した結果、積極的に信仰を持って生きることに意味を見出した哲学者で、実存主義の走りとされています。
ハイデガーはキルケゴールの実存主義的な哲学に大きな影響を受けています。ハイデガー自身も、もともとは神学(キリスト教)の研究者であったため、「キリスト教」と「人間の主体的な生き方」というものを調和させたキルケゴールの哲学には衝撃を受けたのでしょう。
エトムント・フッサール
エトムント・フッサールは「現象学」をはじめた哲学者であり、ハイデガーの直接的な師でした。ハイデガーは、フッサールを「自分に目を与えた」と評していますが、人間が物事を認識する際の主観の重要性に注目したフッサールは、まさにハイデガー哲学の基盤となっているといえるでしょう。
カール・ヤスパース
カール・ヤスパースは、ハイデガーと並ぶドイツの実存主義哲学の代表的論者でした。もともとは精神医学が専門でしたが、ハイデガーとの交流なども通じて、哲学へと没頭していくようになりました。
ハイデルベルク大学で哲学教授となりますが、妻がユダヤ人であったことから、ナチスの隆盛以降は大学を追われ、ヤスパース夫妻も収容所へと送られるぎりぎりまで追い詰められましたが、ハイデルベルクがアメリカ軍に占領されたことで危機を免れました。
戦後は、『責罪論』などドイツの罪と向き合うような政治的著作も残しました。また、ハイデガーと文通を続けましたが、ハイデガーの戦時中のナチス傾倒から、ハイデガーを公然と批判することもありました。
ハンナ・アーレント
ハンナ・アーレントは、全体主義がどのように誕生するかの研究で有名ですが、ハイデガーの教え子でもありました。また、アーレントはハイデガーのファンであり、二人は一時期、不倫関係にもあったことが知られています。
アーレントはユダヤ人であったため、ナチス運動が盛り上がるようになると、アメリカに亡命しました。一方のハイデガーはナチス運動に傾倒していったため、アーレントは胸を痛めることとなりますが、戦後には再会を果たしており、アーレントがヨーロッパに赴く際にはハイデガーにも会っています。
ハイデガーの名言
- 準備中






![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)






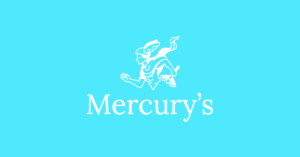




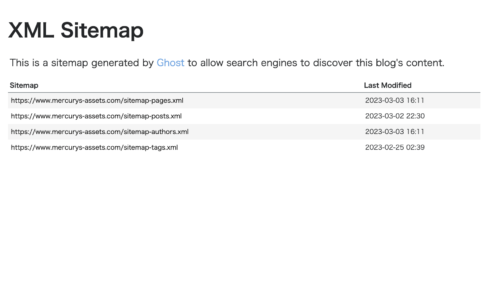


コメントを残す