石燈籠とは

日本庭園の構成要素:石燈籠
石燈籠は、仏教とともに日本に伝来し、神仏への献灯を目的に寺社に置かれるようになりました。
桃山時代に入ると、千利休は石燈籠に灯る明け方の残り火に侘び・寂びの風情を感じ、庭に置いて、夜の茶事の灯りとして用いるようになりました。こうして、露地(茶庭)を構成する要素として石燈籠が庭に取り入れられていきました。
その後の大名庭園などにも、露地(茶庭)が強く影響を与えたことから、日本庭園全般に見られるようになりました。
石燈籠は、上から順に宝珠、笠、火袋、中台、竿、基礎(土台)という6つのパーツを積み重ねて構成されます。また、石燈籠の周りには、燈籠控えの木や灯障りの木といった役木が配植されます。
関連記事
関連参考書籍
本記事を書くにあたり、以下の書籍を参考にしています。日本庭園の種類や歴史、構成要素について、初心者にもわかりやすく解説されています。










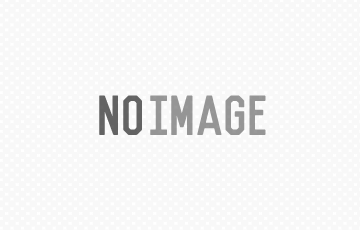

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)






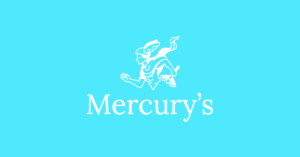




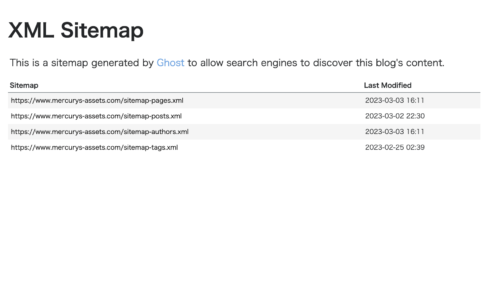


コメントを残す