枯山水とは
枯山水とは、池や水のない日本庭園を指します。
日本庭園の起源は神池・神島にあること等から、もともと日本庭園においては池泉庭園が主流でした。平安時代には庭の東の遣水から水を引いて、南に池、北には山をつくるのが一般的でした。平安時代後期に書かれた『作庭記』には「枯山水」という言葉が登場しますが、これは今のような枯山水庭園を指すのではなく、庭の北部などにつくる水のない部分を指す言葉でした。
現在の枯山水が意味するところの「池や水のない日本庭園」が登場するのは室町時代です。
背景には、室町時代の禅宗の広がりがあります。禅宗では、本来は深山幽谷で座禅の修行を行うことが求められますが、市井に寺院が作られるようになると、深山幽谷を表現するような幽玄な庭が好まれるようになりました。加えて、応仁の乱による京都の荒廃などによって、京都において、池のある立派な庭をつくる力を持つ権力者がいなくなったことも枯山水が登場した背景としてあげられます。
枯山水では、池がない代わりに、枯滝石組で滝を表現したり、砂紋(箒目)によって波を表現することが行われます。
また、枯山水では砂利を敷き詰めますが、当初は白川砂が用いられていました。現在は錆砂利やビリ砂利が用いられることもあります。
関連記事
関連参考書籍
本記事を書くにあたり、以下の書籍を参考にしています。日本庭園の種類や歴史、構成要素について、初心者にもわかりやすく解説されています。











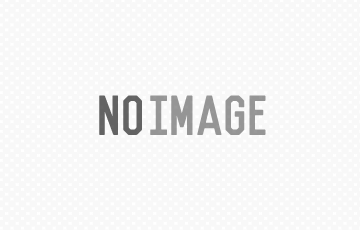

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)






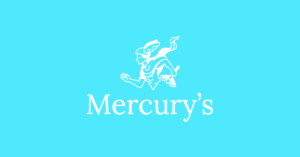




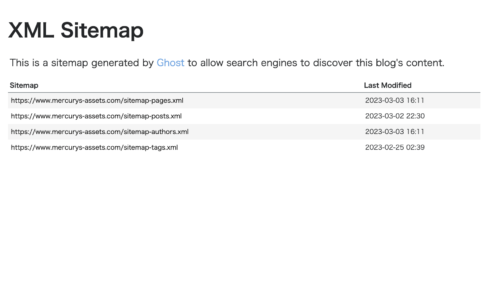


コメントを残す